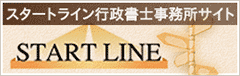遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議がない限り、遺産相続手続きが進みません。その際、目安となるのが法定相続分ですが、必ずしも法定相続分どおりにする必要はなく、法定相続分とは異なる相続割合であったり、相続人の一人に相続させることが可能となります。繰り返しになりますが、遺産相続手続きを完成させるには相続人全員の同意が不可欠です。
目次
1.遺産分割協議の流れ
2.遺産分割協議を上手に進めるポイント
3.遺産分割協議を期限内に行う必要がある事例
4.トラブルになりやすい遺産相続とは
5.遺産分割協議を自分で行うのは大変!?
6.関連するページ
遺産分割協議の流れ
- (1) 相続人全員で協議
- 法定相続分でどんなに相続分が少なくても、相続人全員の合意がない限り、遺産分割協議は成立しません。万一相続人の中に、行方不明者・未成年者・認知症の方などがいる場合、それぞれ不在者財産管理人・親権者又は特別代理人・成年後見人が遺産分割協議に代理人として参加します。
- (2) 相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成
- 相続人全員がいくら合意しても口頭ではトラブルになりかねませんし、名義変更もできません。遺産分割協議書の作成には、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付が必要です。
遺産分割協議書のポイントは次の3つ。
- ・タイトルに遺産分割協議書と書く
- ・遺産を漏れなく書く
- ・相続人全員の署名つと実印の押印が必要
遺産分割協議を上手に進めるポイント
- (1) 遺産分割は必ずしもきっちり平等とはならない
- 相続を想続にするには、相手に対する想いが不可欠です。損得で考えたり、あくまで平等に拘りすぎると、後の相続に影響を及ぼすような遺産相続になり、後の相続においても禍根を残したり、家族関係にも影響を及ぼします。また財産には不動産、金銭、株等がありますが、分割しやすいものもあれば、不動産のように分割しにくいものもありますので必ずしも平等となりにくいことは考えておかなければなりません。
- (2) 隠し事が災いのもと
- 被相続人と同居、あるいは財産管理を行っていた親族が遺産を隠しているのではないか、という他の親族の疑いの気持ちが遺産分割協議で揉める一つの大きな要因となることがあります。 たとえ親族同士とはいえ、被相続人の財産を事実上管理する立場にあった相続人は、他の親族に聞かれる前に財産を証拠書類とともに相続人の前でオープンにするぐらいの気構えをもつことが、円満な遺産分割協議のために重要なポイントです。
遺産分割協議を期限内に行う必要がある事例
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内に行います。万一期限内に遺産分割協議が終わらず申告書を提出しない場合、無申告加算税がかかります。さらに期限内に納税をしていない場合、納税するまでの間の延滞税も発生します。万一期限内に遺産分割協議が終わらない場合(未分割状態)、多くは法定相続分の割合で分割したと仮定して、期限内に相続税の申告と納税を行います。未分割状態でのデメリットは、配偶者の税額軽減・小規模宅地などの特例を受けることが出来ず、一時的とはいえ、多めの税額を負担する相続人が出てくることになります。例えば遺産分割協議の上、相続人4人のうち、1人の相続人に遺産分割することが相続税の期限を過ぎた後にまとまったとしても、いったんは相続財産を受け取らない残りの3人が相続税の納税することになります。但し申告期限までに、相続税の申告書と申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで、遺産分割が成立した日から4ヶ月以内に更正の請求をすれば、特例を適用した相続税を改めて申告できます。払いすぎた税金の変更を求めることもでき、相続税が不足した場合は修正申告して不足分を収めます。
トラブルになりやすい遺産相続とは
①知らない・しばらく会っていない相続人がいる相続 ②被相続人の離婚、再婚 ③相続財産の多くが不動産 ④放置した不動産の名義 ⑤おふたり様の遺産相続 ⑥おひとり様の遺産相続
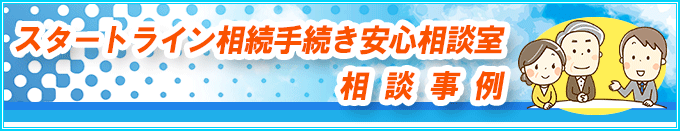
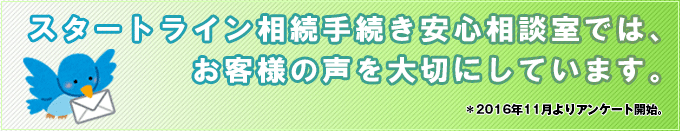
遺産分割協議を自分で行うのは大変!?
上記の通り、トラブルになりやすい事例に該当する場合を勿論のこと、現在円満な関係での相続で安易な法定相続通りの遺産分割は、次の相続や相続税の事を考慮した際にトラブルになることもあります。遺産分割は初めのやり方を間違えると大きなトラブルにもなりかねませんので、専門家の視点をもとにした遺産分割を検討して頂く必要があります。 また遺産分割協議書は一度作成すると、あとでやり直しができなくなるため、後日トラブルにならないような遺産分割協議書作成が必要となります。
こうした負担を軽減する必要があれば、専門家にご相談することをお勧めします。当相談室では遺産相続手続きサポートの中で行っておりますのでお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書の進め方・遺産分割の提案、遺産分割協議書作成は
スタートライン相続手続き安心相談室にお任せください。
関連するページ
ステップ1相続人
調査
ステップ2
相続財産の
調査 ステップ3
遺産分割
協議 ステップ4
遺産名義
変更
よくある質問
| 「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
| 「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
| 「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス

*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン
- JR「田町」駅徒歩約7分
- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!!
相続手続き・遺言・不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください。
東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応
![]()
![]() 受付時間:10:00~19:00(月〜金)
受付時間:10:00~19:00(月〜金)
10:00~17:00(土)
- 誰に頼むか迷ったら
- トラブルを回避する提案力
- 説明や報告しっかりで安心

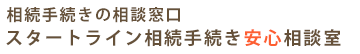


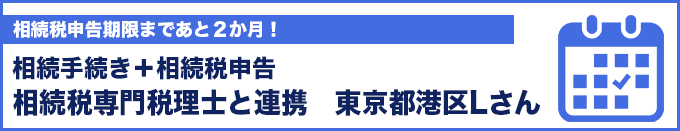
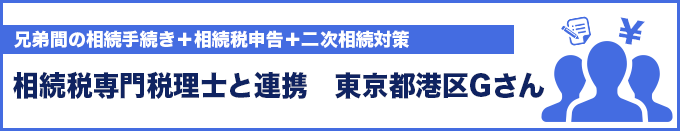
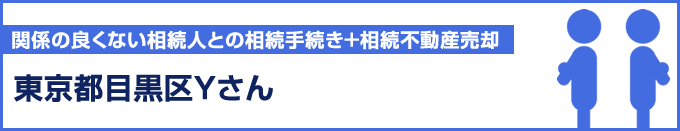

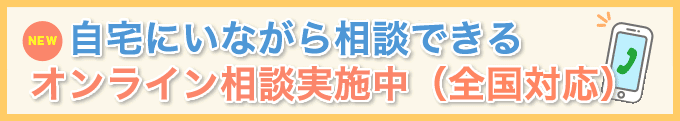
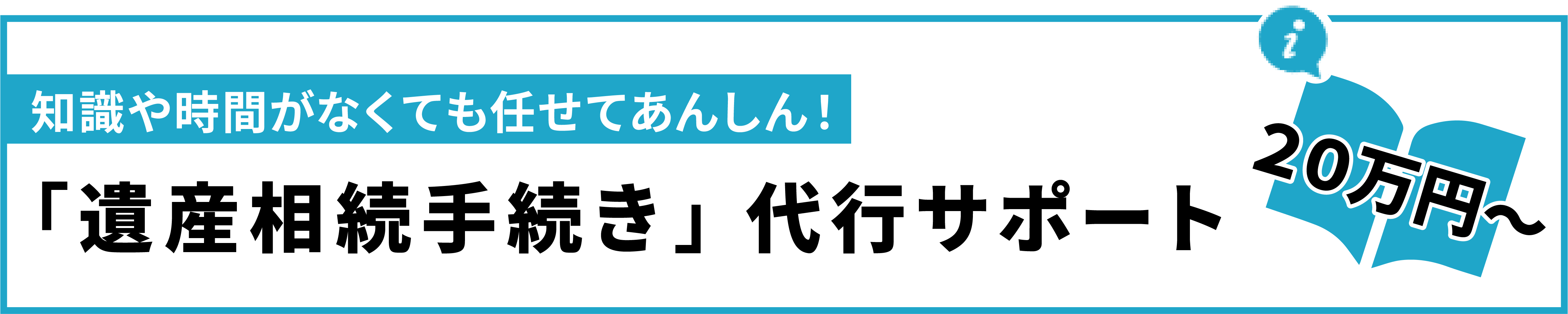
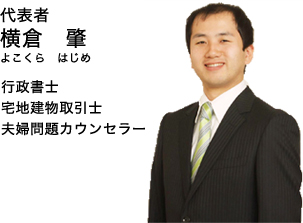


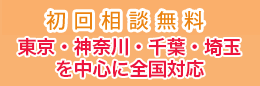
 登録から、
登録から、