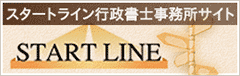「お父様が亡くなられた後、ご実家の不動産の名義をどうすれば良いのか?」
これは、相続のご相談で非常によく寄せられるお悩みの一つです。同居されていたお母様の名義にすべきか、それとも将来を考えて子の名義にすべきか、判断に迷われる方は少なくありません。
相続はご家庭の状況によって千差万別ですが、今回は一つのモデルケースとして、**「基本的にはお母様の名義にすることをお勧めする理由」と、「その後に必ずやるべきこと」**について、行政書士が分かりやすく解説します。

▼本ページの内容を分かりやすく動画にしています。
【モデルケース】
亡くなった方: お父様(自宅不動産はすべてお父様名義)
相続人: お母様、長男、長女の3名
状況: お母様はご実家で一人暮らし。長男・長女は独立して別居。家族関係は良好。

なぜ「母」の名義が良いのか?3つの大きなメリット
お父様の相続(一次相続)において、ご実家の不動産をお母様名義にすることには、主に3つの大きなメリットがあります。
メリット1:相続税を大幅に軽減できる
相続税には、配偶者のための強力な特例が2つあります。
1. 配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産は、「1億6,000万円」または「法定相続分(このケースでは1/2)」のどちらか多い金額まで相続税がかからないという制度です。この制度を活用することで、多くの場合、お母様がご自宅を相続しても相続税の負担は発生しません。
2. 小規模宅地等の特例
お母様がご自宅の土地を相続する場合、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。例えば、1億円と評価される土地であれば、2,000万円として計算できるため、相続税の課税対象額を大幅に圧縮できます。
この2つの特例を適用できるお母様が相続することで、相続税の負担を最小限に抑えることが可能になります。
メリット2:家族円満につながる
ご実家に住んでいないお子様(例えば長男)が不動産を相続すると、他の相続人(長女)が「なぜ?」と不公平感を抱き、トラブルの原因になる可能性があります。
まずはお父様と共に暮らしてきたお母様が相続することで、お子様全員が納得しやすく、円満な相続の実現につながります。
メリット3:お母様の「住む権利」を確実に守れる
お母様がご自身の名義にすることで、将来にわたって安心してその家に住み続ける権利(居住権)が法的に確保されます。これは、お母様の生活の基盤を守る上で非常に重要です。
母名義にする際の注意点と「二次相続」対策
メリットの大きい母名義での相続ですが、将来を見据えた注意点もあります。事前に対策を考えておきましょう。
注意点1:お母様の認知症リスク
もしお母様が将来認知症などにより判断能力が低下した場合、法的な手続き(法律行為)ができなくなります。その結果、老人ホームへの入居資金を捻出するためにご実家を売却したくても、簡単には売却できなくなってしまいます。
【対策】
お父様の相続手続きの時点で、お母様の将来に少しでも不安があれば、**「家族信託」**を検討しましょう。信頼できるお子様(長男や長女)に財産管理を託しておくことで、お母様の判断能力が低下した後も、お子様がお母様のために不動産の売却や管理をスムーズに行えるようになります。
注意点2:「二次相続」で税金が高くなる可能性
お父様の財産をすべてお母様が相続すると、お母様自身の財産と合わさって資産が大きくなります。その結果、次にお母様が亡くなられた際(二次相続)に、お子様たちが支払う相続税が高額になってしまう可能性があります。
【対策】
- 一次相続での工夫:お父様の相続の際に、お母様の今後の生活に必要最低限な預貯金は確保しつつ、一部の金融資産などをお子様が相続しておくことも有効です。 生命保険の活用: お母様が生命保険に加入し、受取人をお子様にしておく方法もあります。生命保険金には**「500万円 × 法定相続人の数」**の非課税枠があるため、このケースでは1,000万円(500万円×2人)まで相続税がかからずに財産を遺せます。
- 生命保険の活用:お母様が生命保険に加入し、受取人をお子様にしておく方法もあります。生命保険金には**「500万円 × 法定相続人の数」**の非課税枠があるため、このケースでは1,000万円(500万円×2人)まで相続税がかからずに財産を遺せます。
【最重要】一次相続が終わったら必ずやるべきこと!お母様の遺言書作成
無事にお父様の相続(一次相続)が終わっても、それで安心ではありません。次にやるべき最も重要なことは、お母様の「遺言書」を作成することです。
注意点1:お母様の認知症リスク
もしお母様が将来認知症などにより判断能力が低下した場合、法的な手続き(法律行為)ができなくなります。その結果、老人ホームへの入居資金を捻出するためにご実家を売却したくても、簡単には売却できなくなってしまいます。
なぜなら、お母様が亡くなった時、そのご実家を「誰が」「どのように」相続するのかを決めておかないと、お子様たちの代で揉めてしまう可能性があるからです。
遺言書で絶対にやってはいけない「不動産の共有」
お子様たちに平等にしたいという思いから、「自宅不動産を長男と長女に1/2ずつ相続させる」という内容の遺言書を作成するのは大変危険です。
不動産を共有名義にすると、売却や大規模な修繕など、何かを決める際に共有者全員の同意が必要になります。
- 兄:「誰も住まないし、管理も大変だから売却して現金で分けたい」
- 妹:「生まれ育った家だから、思い出があって売りたくない」
このように意見が対立すると、不動産は活用も売却もできない「塩漬け」状態になってしまい、兄弟姉妹の関係にまで亀裂が入りかねません。
解決策は「清算型遺贈」
どうしても共有にせざるを得ない、あるいは売却して公平に分けてほしい、というお気持ちであれば、**「清算型遺贈(せいさんがたいぞう)」**という方法があります。
これは、遺言書の中で**「この不動産を売却し、その代金を長男と長女で1/2ずつ分けなさい」**と指定する方法です。
こうすることで、相続人のどちらかが「売りたくない」と反対しても、遺言の内容が優先され、お母様の想いを実現することができます。お子様たちを将来のトラブルから守ることにもつながります。
まとめ:相続は二次相続まで見据えた計画が重要です
お父様が亡くなった際の不動産相続は、まずはお母様名義にすることで、税金の面でもご家族の関係性の面でも多くのメリットがあります。
しかし、それで終わりではありません。その後の認知症リスクや、お子様たちの代で起こりうる二次相続の問題まで見据え、お元気なうちにお母様の遺言書を作成しておくことが、真の円満相続の鍵となります。
相続手続きは非常に複雑で、ご家庭ごとに最適な方法は異なります。少しでもご不安な点があれば、一人で悩まずに専門家にご相談ください。
相続でお困りの方へ。スタートラインが初回無料でご相談を承ります。
私たち行政書士法人スタートラインは、遺産相続の総合窓口として、相続手続きの代行から遺言書の作成サポートまでワンストップで対応しています。
- 経験豊富な行政書士が解決:累計2,000件以上の相続実績。相続人が多い、遠方にいるなど手間のかかる案件もお任せください。
- 不動産に精通:不動産が絡む専門性の高い案件にも対応できるのが私たちの強みです。
- 安心の料金体系:費用は相続財産の額に応じて設定。ご契約前に必ず調査・算出し、明確な料金をご提示します。
- 柔軟な相談体制:初回相談は無料。対面・出張・オンライン・電話でのご相談、土日の対応も可能です。
お一人で悩まず、まずは私たちと一緒に問題解決の第一歩を踏み出しましょう。お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
| 「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
| 「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
| 「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス

*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン
- JR「田町」駅徒歩約7分
- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!!
相続手続き・遺言・不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください。
東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応
![]()
![]() 受付時間:10:00~19:00(月〜金)
受付時間:10:00~19:00(月〜金)
10:00~17:00(土)
- 誰に頼むか迷ったら
- トラブルを回避する提案力
- 説明や報告しっかりで安心

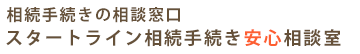



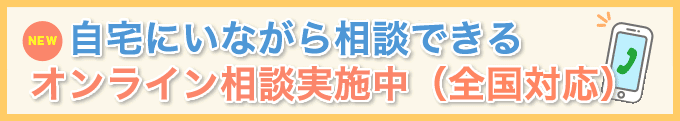
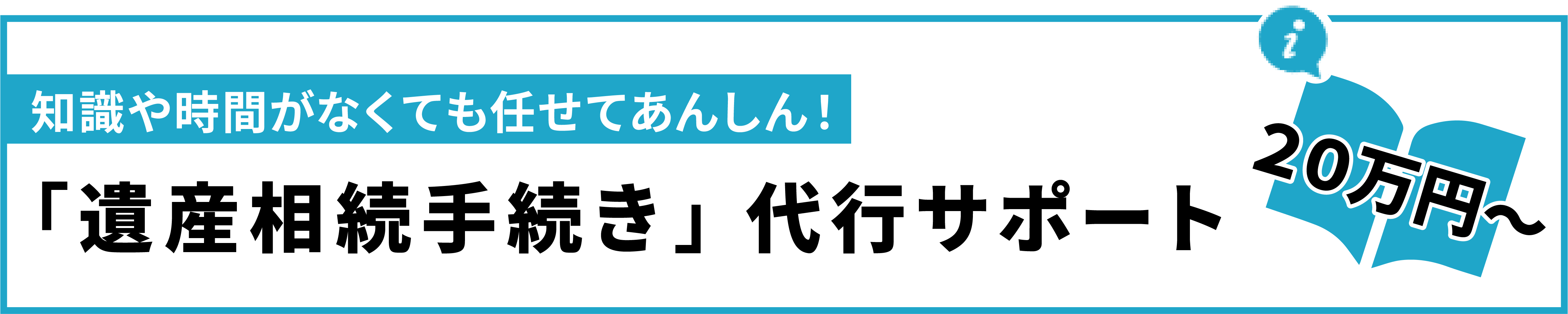
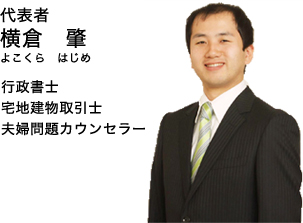


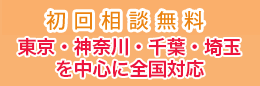
 登録から、
登録から、